2011.10.23 �ߐ{�����z�R�Ղ�K�˂�F��ҁi���̂S�j
�����������

���čz������~��āA��̒��������ł�������₽���Ȃ����{�g���R�[�q�[���J���Ĉꕞ���Ă݂�B
�����͓~�G�ɂ͓��{�C�����琁������G�ߕ��������Ă��� "���̒ʂ蓹" �ɓ������Ă���A�����͐̂̒����Ɠ��������㑤�ɐΊ_��ς�ň�i�Ⴍ�Ȃ����Ƃ���Ɍ����Ă���B�M�҂͏��w�Z�̍��ɂ܂����X�̌������c���Ă���̂������L��������̂����A���݂̔������e���Ȍ@�����ď����̂悤�Ȃ��̂������B

���̂������ɁA�u����������v �ƌ@��ꂽ�肪����B����@�����R�x�����̎��{�����J�������̂ŁA���̏o����H���Ă����Ɛ^�������ɍs�������̂����A�����Ɍ����Ă����ɂ͕����I�Ȑ[���Ӗ��͂��܂芴����ꂸ�A��ʓI�ȎR�̐_�Ƃ����J��ꂽ���̂̂悤�Ɏv����B�����͏��a�Q�N�ƍ���Ă���A�z�R�̌�������̂��̂ł���B
�אڂ���啬�̍z�����猩�ĉN�̕��p�ɂ���̂ŋ��Ȃ̂��ȁc�Ƃ������͎v�����̂����A�ǂ���炻��قǐ[���Ђ˂�͖����悤�ŁA�ǂ���當���ʂ� "������삵�Ă��������܂�" �Ƃ����Ӗ������ł���炵���B

���Ƃ����A��O�͎O�l����������ʂ���R���p�؍ނȂǂ����̔w�ɏ悹�čz�R�ɋ������郋�[�g���������B�c�Ə����� �u���������Ŗ�Ƃ̓P�V�J����!!�v �Ȃǂƕ��S���鎩�̎��R�ی�h�̐l���o�Ă����������A�ߐ{�̎R�x�����������������ɕғ����ꂽ�̂͏��a25�N�̂��Ƃł���A��O�͖؍ނ̔��̂ɓ��ɐ���͂Ȃ������̂ł���B
�O�l�����͖���26�N���ȍ~�A���̍̌@/���B���s���A���������ɂ͐l���̔������z�R�W�҂ł���i���j�B�̌@�ꏊ�͎O�l�����h�̕揊����R���ɏ���������������ŁA�z��͉����ł������B���B�ɂ͔R���Ƃ��Ė؍ނ��ʏ���邽�߂���p�̍ޖ؋Ǝ҂�����A�ߐ{�����z�R�͂�������R���̋��������悤���B
���l���̔����Ƃ����Ă�44����21���Ƃ���������ƃN���X�̋K�͂ł���A����قǂ̑�z�R�Ƃ�����ł͂Ȃ��i^^;�j

�]�k�ɂȂ邪�O�l�������R�͑吳����O���ɂ͑�ꎟ���̎��v�Ɏx�����čD�i�C�ɕ��������̂́A���͎��v�������Čo�c��ƂȂ�A���т��ыx�R�ƂȂ��Ă���B����������̔肪���������a�Q�N�Ƃ����̂͂��̋ꂵ�������ƍ��v���Ă���A�M�ғI�ɂ͂����͂��ƂȂ����̖؍ޒ��B�͓ߐ{�����z�R���O�l�����W���ɍ����L�ׂ��o�ϓI�~�ς̑��ʂ��������̂��ȁc�ȂǂƂƑz�����Ă���B
�O�l�����͉�Ò��X���̉h�͐����ƂƂ��Ɍ���鍡�͏��ł����W�������A���̍Ō�̎p�͂��Ă� "�h�꒬" ����͐����ƕϑJ���āA�z�R�̏W���ł������B�O�l�������R���p�B�ƂȂ����̂����a�Q�X�N�A�Ō�̏Z�����]�o���Ĕp���ƂȂ����̂����R�Q�N�ł��邩��A�z�R����̏I�����������̖��^������t�����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B
�c�����Ă���́A�ߐ{�����z�R�̐����Ƃ��قڈ�v���Ă���̂ł���B
������

���Ă�������͂��悢������Ղ������Ă����B
�z�R�����̊�_�͕�̒����̘e70m�قǂ̂Ƃ���ɂ���A�ؑ��̈�\�Ƃ��Ă͍ł����^�𗯂߂Ă���B�c�Ƃ����Ă��E�i�₮��j�͊��ɓ|�Ă���A�c���Ă���ؑg�݂͗����ςݏo�������̓y����x���B

�ؑg�݂̎��ӂɂ͌����̓y��炵���Αg�݂ƌ@�����̍��Ղ��������݂���B

�������Ă݂�ƁA�z���̎��ӂɂ͌��\�Ȍ������U�݂��Ă������Ƃ��킩��B
���݂͂��̑������P�����ꂽ��|�Ėڗ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă��邯��ǂ��A�z�R�������̍��͂��̕t�߂͂����Ɠ��₩�ɐl�̊�������ꏊ�������炵���B

���ĕ��̋����Ƃ���ł��邹�����A���C���[���[�v���x�����ł��낤�E�����Ƃ����������ē|�Ă��܂��Ă���B���������݂ł����̎c�[�͓_�X�Ɠo�R���ɉ����đ����Ă���A�Ȃ�Ƃ����̃��[�g��ǂ����Ƃ͉\���B
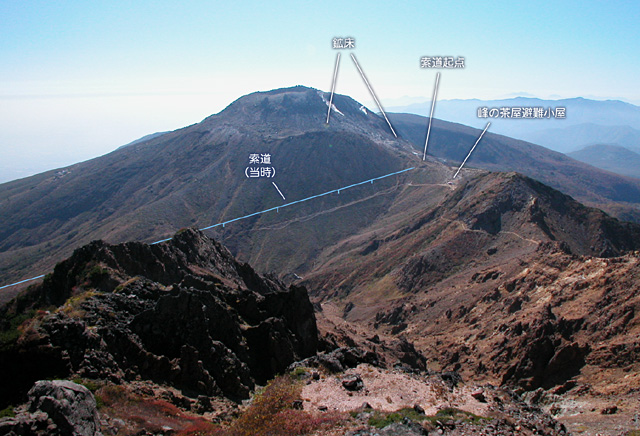
���������̒����x���ʂ���݂�ƁA�����̍����͂��̂悤�Ɍ��������ł���B���ʒn�}�ł̓s���Ɨ��Ȃ����A�������o�R�������͌��\�ȋ}�X�ŁA��̒�������z�R�������ɍ~���ƒ�������1.3km�ɑ��A���̍��፷��260���قǂ��������B
�����̍����́A���̌X�𗘗p���čz��ςނƂ��̎��d�ŃS���h��������Ă������̂������B���܂��l�������̂ŁA�����牽���������グ����ォ��d�ʕ��������z���~�낷�������|�I�ɑ����������߁A����ŏ[���S���i���C���[�j�����������邱�Ƃ��o�����̂ł���B�N�ԉ��S�g�����̍z���^�������̂ɓd�C����R�����������Ȃ������Ƃ����̂͌��\�X�S�C���ƂŁA��������������Ƃ̉��P�����Œ�Ă�����ԈႢ�Ȃ����ʏ܂����炦�邾�낤�B
�Ȃ������͊�{�I�ɂ͉����p�ł��������A�y�ʂȉו��ł���Ώ�葤�̃S���h���ɐς�ň����グ�邱�Ƃ��ł����B�����̃T�C�_�[�Ȃǂ͐l���S���ň����グ����A�����ɊԎ肵�Ď����グ���ق��������I�ȋC�����邯��ǁc���ۂ͂ǂ��������̂��� �i^^;�j

����������ȑn�ӍH�v�̂������������A���ł͂������蕗�����Ă���ȏ�ԂɂȂ��Ă���B�����m��Ȃ��l����������Ă��A�����̘E�ՂƂ͂ƂĂ��v��Ȃ����낤�B

�S���i���C���[�j���x����E�͐̂̎ʐ^������ƍ������W�`�P�Om�قǂ���A�O�p���̂Ă���Ƀ��C���[�v�[���[���x����������A�����e�i���X�p�̒�q���t�����`������Ă����B���͓d�M�����炢�̑������������悤�����A���݂ł͕\�ʂ��������Ĕ����ꗎ���c�̕������������ׂ��c���Ă���ɉ߂��Ȃ��B

�E�͂܂����̐��{���炢�͂��낤���ė�������Ԃ��ێ����Ă��邯��ǁA�������Ɖ��N���ۂ������ɂȂ��B�c���������|��Ă��܂��A���Ƃ͖��[�݂����Ȕj�Ђ����ɔ����Ȃ��狀���Ă����݂̂ł���B

�c�����Ȃ�ƁA�������̔����ȍ��Ղ��m�F�ł���Ō�̎����c�Ƃ������ƂɂȂ�̂�������Ȃ��ȁB
���R�_�̔�

���ēo�R���������Ă���ƁA�₪�ĐX�ь��E��������ĖX�̂Ȃ���i�ނ悤�ɂȂ�B�����Ȃ�����\�y���ێ�����ĕې��͂��ۂ����̂����̕t�߂���ł���B�z�R�������Ղ܂ł͂��Ƃ킸�����B

�₪�Ď������ɔ����钼�O�ɁA�傫�Ȋ�������Ă����J�[�u������B�����ɏ����Ȑ_�Ђ�����A�R�_���J���Ă���B�����z�R�̎В������]�ƈ��̈��S���F�肵�Č����������̂Ƃ����A�����炭�͔w��̑�₪��_�̂Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤�B�����͎��R�őf�p���p�c�i�ڂ��Ƃj�ɑ��삳��A�S�Ȃ��������̐Αg�݂z������B�z�R�炵����Ɉ�ꂽ�_��ł���B
�����͗����z�R���R������͒��炭���ɖ�����Ă������A�R�x�~�����ɂ��o�R�������ɔ���2009�N�ɎG���̒����甭�@���ꂽ�B���݂ł͂����������A�z�R����̈�\�̒��łقڗB��A�����̎p���̂܂܂ɐ�������ۑ��̑ΏۂɂȂ��Ă���B

��͎��R�̕\�ʂ� �u�R�_���v �Ƃ̂@���Ă���B�u���v �͕����̕\���Ȃ̂Ő_�������ȍ~�Ƃ��Ă͂�����ƕςȂƂ��낪����̂����A�����炭�͒��J��݂����Ȋ��o�̂��̂ł���قǐ[���Ӗ��͂Ȃ����낤�B
��̓I�ɂǂ�Ȑ_�l���c�Ƃ����\�L�͎c�O�Ȃ���Ȃ��̂����A�R�_�Ƃ͓��ɒf�肪�����ꍇ�؉ԍ��P�i���̂͂Ȃ�����Ђ߁j���w�����Ƃ������B��/��/���Ȃǂ̋����n�̍z�R�ł͋��R�F�_�i���Ȃ�܂Ђ��̂��݁j�A���R�����_�i���Ȃ�܂Ђ߂̂��݁j���J�邱�Ƃ�����̂����A�����͔�����Ȃ̂ł���ɂ͓�����Ȃ��C������B
���c���A���������В����͂����܂Ő[���l���Ă��Ȃ������c�Ƃ����̂���ԗL�蓾�����ȃI�`�����i^^;�j

���̎R�_��̐ݒu�̗R�����L����������A�����e�Ɍ����Ă���B�o�R�҂��ڂɂ���ł��낤�ł��ڂ��������z�R�ɂ��ď����ꂽ��������A�����܂ł���̕����ɂ��ď����ꂽ���̂ōz�R�ɂ��Ă̏ڍׂ܂ł͂킩��Ȃ��B���������ꂪ���邱�Ƃōz�R�̑��݂�m��o�R�҂������A�����Ȃ������R�N�O�ɔ�ׂ���y���ɏ͉��P���Ă���B

�����Ă��܂�R�̐_2.0�Ƃł������ׂ��V���Ȕ����������c

���U�ƎГa���Č�����Ă���B�ǂ����Ă���ȑ��Ȃ̒c�n�݂����ȏɂȂ��Ă��܂��Ă���̂�����͂悭�킩��Ȃ�����ǁi�j�A�܂������ł��_�l�̋��S�n�ɋC���g���ēo�R�҂̈��S���F�肵�Ă���̂��낤�Ɖ��߂�������

�Ȃ��ē��ɂ���z�R���Ǝ����������S�T�N�`�Ƃ����͓̂ߐ{�̗����z�R���̂��̂̎n�܂���w�����̂ł͂Ȃ��A�����炭�͐��܂Ō����������ߐ{�����z�R������Ђ̑n�Ǝ������w�����̂��낤�B�ߐ{�ɂ͂����ЂƂ����R�z�R�i�c�O�Ȃ���ڍׂ͂悭�킩��Ȃ��j�Ƃ����̂�����A��͂艌���@�ʼnΌ��������̌@���Ă����̂����A������͖���20�N�ォ�瑀�Ƃ��Ă����B
���������̍z�R��Ђ͓ߐ{�Ŗׂ���������k�C���̏\���x�ɓ������ĐV�z�R�𗧂��グ����ɁA���̏\���x�����i�吳15�N�j���đ����̎����҂��o���A�z�R���Ƃ���͓P�ނ��Ă���B���ǁA�l�X�̋L���ɂ��낤���Ďc���Ă���͍̂Ō�܂Ŏ��Ƃ��p�������ߐ{�����z�R������Ђ̂݁c�Ƃ����̂����ԂŁA����ȏ�̂̂��ƂƂȂ�Ƃ�͂薶�̔ޕ��Ȃ̂ł���B
���ӂ����сA���̒����ɂ�

���Ē��X�Ƒʕ���A�˂Ă������A���낻����߂�����Ƃ��ē��̒����ɂ��ċL���Ă݂悤�B�R�_�̔�̂�������ɁA�Âт������ƒ���������B�Ƃ��ɍz�R����̈╨�ł���B�_���I�ɂ͂�������オ�_��ł���A�������牺�������Ƃ������ƂɂȂ�B
���̒������牺��200m�قǂ��A�����z�R�̃x�[�X�L�����v�Ƃ������ׂ� "���̒���" �n��ƂȂ��Ă���B�������ɗ����� "�Ō�̋����|�C���g" �����˂Ă���A�����͐l���؍݂ł��邬�肬��W���̍����ꏊ�ł��������i���݂ł͊ȈՏꂪ�����Ă���ڈ���ł����ł͂Ȃ��j�B�����ɍ�ƈ��h�ɂ⎖����������ꂽ�̂́A�Ȃɂ������̐��̋������ő�̃|�C���g�������ƕM�҂͍l���Ă���B

�����̐��ʂɂ́A�o�R�w���Z���^�[�̌���������B�w���Z���^�[�Ƃ����Ă��l������̂��������Ƃ������̂����i^^;�j�A���������Ă̍z�R�������̐Ւn���B
�R�������牺���Ă��������͂��̌����̗��肪�I�_�ŁA��������ςݍ~�낵�������z�͌��݂̉��n�̃X�y�[�X�ɉ��u������Ă����B

���̉��n�̂Ȃ��ŁA�����̂����p�����Ă̍�ƈ��h�ɐՂł���B���̒����ŕ������Ƃ� ��A�����ɏ풓���Ă�����ƈ��͂W�O���قNj��������ŁA���̑��ɖ��H����ʂɂ��яꂪ����l�������Ă����Ƃ����B������܂߂����l�����ǂ̂��炢�ł������̂��́A�c�O�Ȃ���悭�킩��Ȃ��B

�����̐��ʂ�����ʘH�����Ẵ��C���X�g���[�g�ł���B���{���狌����o���Ă���ƁA�ۑ��ō��ꂽ�ȑf�Ȗ���������Ă��̒����O���Ƃ���A���B���A��ƈ��h�ɂ��o�Ď������ɂ��ǂ蒅�����B���Ă͊ό��o�R�҂����������s�������Ă���A���y�Y����ɗ����̉�������肵�Ă����炵���B

���B���̐��m�ȐՒn�͂ǂ̂�����ł����A�ƒ����ŕ����Ă݂��Ƃ���A�����ł���Ƌ����Ē������̂����̒��ԏ�ł���B���݂͒����Ŏg�p���Ă���ʐψȊO�͑��Ŗ�����Ă��܂��Ă��邪�A���Ă͂����ɐ������������ė����z���Ă��A�������K�X���p���ď������Ă����B���������̏��x�͉Ό������Ƃقړ���99.6%���x�̕i���ł������Ƃ����B
�����̉^���̕ւ��l���Ă̂��Ƃ��A�������郁�C���X�g���[�g�ɂ͂�邢�X�����Ă���B�c����́A�n�}������������n�̏������ق������o�I�ɔ[�����₷���B���B�����牺�葤�̍�����_����ԏ�܂ł̓������A���ɃX���[�Y�ɂȂ����Ă���B

����ł͌��݂̑�꒓�ԏ�̃X�y�[�X�͉����������Ƃ����ƁA�Ȃ�Ƃ����������z�����Ȃ̂ł���B���������C�̏o��z���i�����R�j�ł͂Ȃ��A�z���@���Đl�דI�ɏĂ��Đ��B������^�C�v�̃��}�ł������B����͕M�҂����߂Ēm�������ƂŎv�킸�����̕��ɉ��x���O�������Ă��܂����̂����A�ԈႢ�Ȃ��Ƃ̂��b�������B
�܂肱�����A���h�ȎY�ƈ�\�Ȃ̂ł���B���ԏꂪ�ׂꂽ�Ђ傤����݂����ȕςȌ`�����Ă���͓̂����̘I�V�@��z��̌`�����̂܂p�������̂炵���A����͂���ŋM�d�Ȃ��̂��B�Ȗ،����̉��̍H�v���i�����j�d���U��ɂ́A��͂芴�ӂ��Ȃ���Ȃ�܂� �R�i�L�́M�j�m

���߂āA���ԏ�ɍ~��Ē��߂Ă݂�B���̒m�����Ȃ���A�����̓I���V�[�Y���ɂ͊��X�����a�̃^�l�ɂȂ邽���̒��ԃX�y�[�X�ɂ����Ȃ��B���������ꎩ�̂��z�R�Ւn�ł���ƒm��A�Ȃɂ��X�^�X�^�ƎR����ڎw���������ό��ł͂Ȃ��Ǝv���邾�낤�B

����ɂ��Ă��c����œߐ{�̍z�R�̑S�̑��Ƃ������̂���������Ɩ����Ȃ��킩�����悤�ȋC������B��������P���ɉΌ���ڎw�������Ȃ�s�l����ʂ����ق����ߓ��Ȃ̂ɁA�Ȃ��k����̃��[�g���I�ꂽ�̂��B�܂��ǂ����Ă����ɍz�R���������u����x�[�X�L�����v�����i�̂��B�z���͎R���ɂ���̂ɁA�Ȃ����B���������ɒu���ꂽ�̂��B
����́A�������̂����łɂЂƂ̍z�R�ŁA�@��o���������z��~�n���Ő��B���鍇���������������ƁA����ѐ��̕⋋���ł������ƁA�����ĎR���̉Ό��܂ł��k���P���Ԃ̒ʋΌ����ő�ʂ̍�ƈ����풓�ł������Ɓc�܂�A�����������ƂȂȁB

�c����Ȃ킯�ŁA�M�������Ă����̂� �u������I�v �c�ŐV�������፬���̒���MAP������Ă݂��B
���ɍ��ꂽ�ό����[�v�E�F�C�ƃ{���P�[�m�n�C�E�F�C�������Ă݂�A�������z�R�Ƃ�������Ŗ���������{���łȂ������y�n���ł��邱�Ƃ��킩��B����߂Ă݂āA��͂�A���ߐ{�͊ό��ȑO�ɍz�R�̎R�Ȃ̂��ȁc�Ƃ�����ۂ��A�M�҂͐[���������̂ł������B
�������ݘb�̃G�s���[�O

���Ă������������ɒ����Ȃ��Ă����̂ł��̕ӂň���ɂ������i^^;�j�B�Ō�ɒ����ŕ������炦�����Ȃ���A�����m��Ȃ��o�R�q���������đ����̃��^�b�������B��͂�Ƃ������A�g�t������ړI�ɗ��Ă�����X�́A�����z�R�̑��݂��قƂ�ǒm��Ȃ��B
�u����ȂƂ���ʼn����̂ꂽ��ł����v
�u�����ł���v
�u�ւ��c�I�v
�c����Șb�����Ă���ƁA�ʔ������������̎�l�����P���̎ʐ^�������Ă��Ă��ꂽ�B

�T�O�N�O�̎ʐ^�ł���A�Ƃ������̎ʐ^�Ɏʂ��Ă����͓̂~�G�̖��Ԓn���̍z���ł������B�����@�ł����ؖ@�ł������̐����͎��R��p�Ő͏o��������̂Ȃ̂ŁA�I���V�[�Y���͓~�G�������B���̎ʐ^�͐��V�̓���I��ŎB�e���ꂽ���̂̂悤�����A�ߐ{�R��͓~�G�ɂ͐�_�ɕ����邱�Ƃ������A���������B�����č~���͕X�̗���������悤�Ȓɂ��Ŗj��ł̂ł���B
�c���̃��}�ɁA�������̍z�v�������ʂ��Ďd�������Ă������オ�������̂ł���B�d�C���ʂ��Ă��Ȃ���������A�l�͂Ɩ����͂̍����ŁA�N��1800�g�����z���闰������������o�ׂ���Ă����B�R���t�߂ɂ�������\�̂������́A����ȕ��i�̒��ō�ƈ����g���Ƃ����x�e���ł������ɈႢ�Ȃ��B

�ό��o�R���嗬�ƂȂ������݁A�~�G�̃{���P�[�m�n�C�E�F�C�͎��Ɨp�Ԃɂ�闈�q �i�����m�[�}���^�C���œo���Ă���`�������W���[�Ȑl������^^;�j ����ɂ��āA��ۉ���㑤��������Ă��܂��B�z�R����Ɣ�ׂ�Ɛ�����O���Ŏ~�߂��Ă��܂����A����������͐��ɊJ���ꂽ�ԓ��̋K���ɉ߂����A�k���œo��o�R���͐^�~�ł��Ό��܂ŕ����čs����B
�c����́A���ł͖Y����Ă��܂��������z�R�́A�قƂ�ǍŌ�̒u���y�Y�̂悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B
�����ݘb�ɉԂ��炩���Ȃ���A�M�҂͂���Ȃ��Ƃ��v���Ă݂��B
<��>
�����Ƃ���
�����ƒP���Ɍy�₩�ɂ܂Ƃ܂邩�ȁc�Ǝv���Ă����{�e�ł����A�\�z�ɔ����ăc���R�~���̃��|�[�g�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�ǂ����R���p�N�g�ɂ܂Ƃ߂�˔\�������悤�Ȃ̂ő��ς�炸�_���_���C���ł������A�܂�����͂����̂��ƂȂ̂� �u������I�v �Ɗ���邱�Ƃɂ������܂��傤�i�j
���ĕ��i����ߐ{�̎R�X�c���ɒ��P�x���ӂ͂悭�����Ƃ���Ȃ̂ň�ʂ�`�F�b�N�|�C���g�͌��Ă�����肾�����̂ł����A���\�Ȍ����Ƃ��A���߂����Ƃ����̂͂�����̂ŁA����͕����ʂ� "���䉺�Â�" ���������邱�ƂƂȂ�܂����B�M�҂͓ߐ{�̓o�R���Ƃ����̂͊�{�I�ɎO�l�����h�̗����ȍ~�A�����R/�����R�̐M�o�R�ŊJ���ꂽ���̂Ǝv���Ă����̂ł����A�����z�R����������Ɋ֗^���Ă���悤�Ȉ�ۂł��B��̒������狍������ʂ̃g���b�R�O���Ȃǂ͂܂��ɂ���Ȏ���̂悤�Ɏv���܂��B

�Ƃ���ō���̒����ōŌ�܂œ�̂܂c�����̂����̒����̗����z���̊J�������ł����B�����̓i�j�Q�ɏd�v���_�ŁA���݂̎�v�o�R���[�g���z�R����̉Ό��A�v���[�`���[�g�͂������o�R���邱�Ƃ��Öق̗����Ƃ��Ă��Ȃ���ΐ������܂���B����͑������������ɋ��_�����i���̂Ǝv���A����������ƍ��H�ˎ���ɓ��{������̃A�v���[�`���s��ꂽ���ɂ͑�֒e�E�q��̊J���z�惊�X�g�ɓ����Ă����̂�������܂���ˁB
�����z�R�̂���������₷���̂͂�͂�R���t�߂̈�\�ŁA�X�ь��E����ł��邽�߂ɐΑg�݂Ȃǂ����ɖ�����Ă��炸�A���Ɋm�F���₷���ƂȂ��Ă��܂��i�Ȃ��K���ɖ�����͂���܂����c^^;�j�B���������o�R�����̂ɂ���ɋC�������X���[���Ă��܂��Ƃ����͔̂��ɖܑ̖����b�ŁA���ʂɓo�R��������Ă��邾���ōz�R�̎Y�ƈ�\���������o�R���Ă����̂ł�����A�ق�̐������A��̒i�����������n���Ă݂�]�T�������������̂ł��B

�Ƃ���Ŗ{�҂ł͗����̗p�r�ɂ��ĉΖ�̎����������グ�Ă��܂��܂������A�����p�Ƃ��Ă͍����S���ւ̓Y���܂Ȃǂ̍H�Ɨp�r�̑��A�}�b�`�Ȃǂɂ����L�����p����Ă��܂����B���������a�Q�O�N�キ�炢�܂ł̓}�b�`�͂܂��܂������Ȃ��́i�A�o�p�����\�����j�ō����ł͈�ʂɂ͕��y�����A���ۂɎg���Ă����̂� �u�t���v �Ƃ�����ȈՂȂ��̂ł����B�ǂ̂悤�Ȃ��̂��ƌ����ƁA������������ނ̒[�ɗ�����h��������̂ŁA������A�C�X�̖_���炢�̕��Ŋ����ĉN�����Ɏg�����̂ł��B��ʏ����ɂƂ��Ă̗����́A���̕t���̃C���[�W�ŗ�������Ă����悤�Ɏv���܂��B
�t���ɂ̓}�b�`�̂悤�ɖ��C�Ŕ�����悤�ȋ@�\�͂Ȃ��A��ɗ������������傢�ƐG�ꂳ���ĔR�Ă����A������}�i���܂ǁj�Ɏ����Ă����ĕ����t���Ɏg���܂����B���Ԃ��Ȃ����̓ߐ{�n��ł͂ǂ��̉ƒ�ɂ��܂��͘F��������A�D�̒��ł̓I�L���M�������Ă����̂ł������ɂ��������ł��B
�c�Ƃ����Ă��A���ǂ��̎Ⴂ���i�c���āA���̌������C�����Ȃ��F���j�̓I�L�Ƃ����Ă��s���Ɨ��Ȃ���������܂���ˁB�Y�̔R�Ă��i��ŕ\�ʂ������Ȃ�����Ԃ̂��̂��Â����t�ŃI�L�Ƃ����܂��B���̏�Ԃł͒Y�͓������ԔM���Ȃ�������₩�ɒ����ԔR�Ă𑱂���̂ŁA����������t�i���ԁj��悤�ȏĂ���������̂ɂ͏d�܂����B����ɂ��̏�Ԃň͘F���̊D�������Ă����ƈꒋ�邭�炢�͔M�������Ă����̂ŁA�t���Ƒg�ݍ��킹��Ɣ��Ƀ��[�Y�i�u���Ȓ��Α��u�ɂȂ����̂ł��B
�c�ɂ̔_�ƂȂǂł͂��ꂪ���a40�N�㍠�܂Ō����Ŏg���Ă���A�M�҂̖�k�l���g���Ă��������Ȃ̂ł����A�M�҂͑䏊�̉Ή��v���p���K�X�̋L����������܂���B�t���̎����m���Ă��邩�ǂ����ŗ����z�R�ւ̑z���Ƃ����̂�������������̂ɂȂ��Ă���悤�ȋC�͂��܂����A�c�O�Ȃ���M�҂ɂ̓J�^���O�X�y�b�N�ȏ�̂��Ƃ͕�����Ȃ��̂ł����B

���ēߐ{�Ɍ������b�ł͂���܂��A���{�̗����z�R�͐�㋣���͂��������a40�N��ɂ͂���������ł��Ă��܂��B���Ƃ��ƃA�����J�A���L�V�R�Ȃǂ̑�K�͍z���ł͊ȕ�/�����ȃt���b�V���@�i���j�ŗ������̌@����Ă���A��セ��炪���{�s��ɓ����Ă������ƁA����я��a30�N��Ɍ��Q��Ƃ��Ă̐Ζ������̒E�����u�������i��ł��̕��Y���Ƃ��Ĉ����ȗ������s��ɗ��ʂ������Ƃ����̌����ƌ����Ă��܂��B
�Ƃ���œߐ{�����z�R������Ђ̗����̌@�́A�R�_�̔�̉���ɂ��Ə��a23�N�ŏI������悤�ȕ\�L�ɂȂ��Ă��܂����A�ǂ����̍��̏��R�l�̂悤�ɂ�����ˑR�|�b�N���Ƌ}��������ł͂Ȃ��A���w��ЂɈߕς������葼�Ђƍ��������肵�ĉ����[�u���}���A�ׁX�Ƃ͑����Ă����悤�ł��B�������₪�Ă���������s���Ȃ��Ȃ�A�����ɕR�ƂȂ����̂����a�R�T�N���ł����B
���̊ԁA���Ēn����x�����z�R�Ƃɕς��V�����Y�Ƃ̑n�o���ۑ�ƂȂ�A�ߐ{���A����ѓȖ،��͊ό��J���̂���w�̐��i��}�邱�Ƃł��ٗp�n�o��ڎw�����ƂƂȂ�܂����B���̍��܂łɂ͓ߐ{�n��͍������������i�ݐV�K�̓y�n�����Ȃǂ͓���Ȃ��Ă����̂ł����A����͍z�R�{�݂̐Ւn�����p���邱�ƂŃN���A�����悤�ł��B�������čz�R�Ւn�����p���Ȃ���A�V���ɗL�����H�i�{���P�[�m�n�C�E�F�C�j�A�ό����[�v�E�F�C�Ȃǂ���������A�o�X�H�����J����Ă����܂����B
�L�����H���J�ʂ����̂͏��a40�N�c�z�R�����ƒ�~�����T�N��̂��Ƃł��B����ȍ~�A"�L���Ȏ��R" ��S�ʂɉ����o���ēߐ{�i���ɉ��ߐ{�j�̊ό��J���͈�C�ɐi��ł����܂����B
�c�����āA�z�R�̑��݂͎���ɖY�ꋎ���Ă������̂ł��B
���t���b�V���@�F�����̐����C��n���̗����z���ɐ�������ŗn�Z�A���o�����ĉ������̌@���@�B

���ăI�`�炵���I�`���Ȃ������Ȃ̂ŁA�Ō�ɕ��C�E���玝���A����������R�Ă����Ă݂��ʐ^���f�ڂ��Ă݂܂��傤�B�L�ŃK�X���o��̂Œ��ߐ��������ł͐�ɐ^�����Ȃ��ŗ~�����̂ł����A������Ɨ����̉�̓N���[���̂悤�ɂӂ��ƗZ���āA�������o���Ă����ƔR���n�߂܂����B
�c���ꂪ�A�ƂĂ��_��I�Ō��z�I�ȐF�Ȃ̂ł��B���B���ŏĂ��ꂽ�z���A��͂肱��ȐF�ŔR�����̂ł��傤���ˁB����ɂ͕����钃�P�x�̖�i�ɂ��A��͂肱��Ȑ������������̂ł��傤���B
���ł͂����A�킩��܂���B�c���Ă���͕̂�����ʈ�\�݂̂ŁA���L���Γ͂������Ȏ���Ȃ̂ɐl�X�̋L���͞B���ł��B�����n�̊ό��W�҂����͐����オ�i��ł��āA�M�҂͂S�T�Ԃقǂ����Ă���������ނ��ĉ�����̂ł����A�z�R�����m��l�͖{���ɏ��Ȃ��B�����ЂƂ̎��オ�m���ɉ߂��������̂��ȁc�ƁA�s�v�c�Ȋ��S���c�����ł����B
�ȑO����������S���̍��ł��������悤�ȋC�����܂����Y�ƈ�ՂƂ����͔̂p�Ƃ�������͑e��S�~�݂����Ȉ������܂��B��������z���Ĉ��̎��Ԃ��o�߂���ƍĕ]������ĕ����I�ɕۑ�/�������s���邱�Ƃ�����̂ł����c�ǂ����ߐ{�����z�R�͂��������]�����邱�ƂȂ��Â��Ȃ镗���̓r��ɂ���悤�ł��B�܂������������̘b�����������Ă����̂����R�̓�����c�ƌ�������̒ʂ�Ȃ�ł����ǂˁi^^;�j
<�����܂�>


















