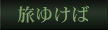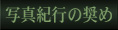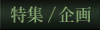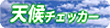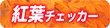2007.04.30 那須疏水を尋ねる(その5)
■三区町

那須開墾社のエリアに入ると、あたりの景観はそれまでの牧草地から水田や畑に切り替わる。ちょうど田植えの時期でもあり農家は忙しそうだ。これは三区町のあたり。

那須疏水は、どんどん分水されていく。背割りによる分水の仕組みは上流側と変わらない。細長いプール状につくられた疏水本流から水が溢れ落ちるタイミングでブレードによって水流を分割し・・・

そのまま並行して引っ張っていく。

本流は地面の傾斜に合わせてどんどん段落ちしていくが、分流は水面水準を水平に保ったまま頑張る。

そして地表水準が分水点を下回ったところで耕地に乗っていく。規模は数百倍?ほども違うけれど、那珂川の取水口と原理はまったく同じだ。むしろこの分水方法をあそこまで巨大にして那珂川に応用したスケールのほうに感服してしまう。

こうしてかつての荒地は豊かな水で満たされていく訳なんだな…。
■二区町

三区を通過して、二区に入った。ここでも水を湛えた水田がひろびろと広がっている。

新幹線の軌道がみえてきた。あれを越えるとまもなく大田原市域に入ることになる。

ここでかなり大きな分配費で疏水は三方に別れた。もうそろそろ地下水の使える地域でもあり、最後の大盤振る舞いといったところだろうか。

西堀本流はいよいよ東北本線(宇都宮線)、そして新幹線を越えて南下していく。

それにしても、ずいぶんか細い流れになったものだなぁ・・・
■一区町

さてそろそろ一区町である。流れの脇に、記念碑が立っていた。通水拾(十)周年記念と書いてある。那須疏水の最初の開通のことではなく、どうやら戦後に行われた土地改良事業についての記念碑らしい。
那須疏水は初期の頃には末端まで水が届かないこともしばしばで、通りを一本隔てて水利権で対立するようなこともあったらしい。特に一区の西堀の東岸側に入植した新規参入組は水利権がもらえず苦労をしたようである。このあたりは調べだすときりがないと思うので、後日余裕があったら調べてみよう。

さらに下り、R461:野崎街道に到達した。旧奥州街道である。那須疏水はこの下に流れ込んでいる。

・・・が、反対側には流れ出していなかった。

なんと、ここで那須疏水は暗渠(あんきょ)になってしまうのである。

それまでのルートから直角に曲がり、野崎街道脇を市街地方面に流れている那須疏水。なんだか、あんまりな扱いだなぁ・・・(T_T)

では野崎街道の南側の水利は・・・? というと、そこにはモーター小屋(ポンプ小屋)があった。
そう、ここではもう地下水が使えるのである。
<つづく>